2024/10/03
いつも『あきたDX通信』をご覧いただき誠にありがとうございます。
昨年10月から二代目主幹を務めている五十嵐です。
現在もたまに営業コラムに顔を出していますが、このメルマガに関しては裏方仕事が多いです。
以前メインコンテンツの「いがらし部長」という名前で登場していましたが、現在はかわもと部長が立派に頑張ってくれています。今回はメインなので緊張していますが、よろしくお願いします。
<100回の意味>
前回の発行で、この「あきたDX通信」も100回目の発行ということで節目を迎え、今回新たなスタートの特別寄稿を僭越ながら飾らせていただく訳なのですが、『100』という数字にものすごく節目感を覚えるのは何故だろうと皆さんは不思議に思いませんか?
困った時はそうコレ。ChatGPT先生に尋ねてみましょう。「100に込められた特別な意味について教えて下さい」・・・すると、なるほどと思われるものが並びます。
1. 完璧さや達成の象徴
2. 整数としての節目
3. 歴史的・文化的な象徴
4. 宗教的・精神的な意味
5. 経済やビジネスの分野
6. 慣用句としての表現
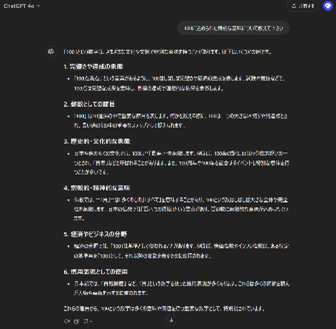
(ChatGPTキャプチャ画像)
我々は様々な背景から「100」に特別な意味を感じているんですね。今回の100回記念は、歴史的・文化的象徴の意味合い(というにはまだまだ浅い連載実績ですが)でしょうか。今後このあきたDX通信が、形は変えつつも末永く後輩達に受け継がれてゆき、単位が「回」ではなく、『100周年記念号!』となれば嬉しく思います。
まずはこれから先の150回、200回、10周年を達成してからですね。
余談ですが「101」という数字にも、101匹ワンちゃん、101回目のプロポーズ(古い)など、たまにタイトルで見かけますが、これも区切りの後の再スタート的な意味なのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
<この一年の振り返り ~DXの浸透と実感のギャップ、そして課題(1)~>
さて、話は変わって、私が主幹を務めることになった昨年の10月からを振り返ると、「DX」というキーワードが完全に定着したなと思える一年でした。
「一般社団法人 秋田デジタル利活用推進協会」(旧秋田RPA協会)が毎年行っている「秋田県内における IT/DX の導入実態に関する調査」(今回で第5回)の公式リリースを見ても、DXの浸透度合いが分かるキーワードが並びます。
特に「DXの認知率は9割を超える、取り組みも51.4%と過半数を超える」という認知率の高さは凄いです(と思いませんか?)。
(秋田デジタル利活用推進協会 2024年8月20日「【ニュースリリース】「第5回秋田県内におけるIT/DXの導入実態に関する調査」調査結果」)
私自身も含め、「DX」というキーワードに対する印象だとか理解は、個人差がかなりあると思っており、「デジタルによる変革」だとか「デジタル主導の○○」だとか、なんだかイメージのしにくい、ぼんやりとした表現・言葉だと思っています。
あくまで私の現場の実感ですが、実際に営業現場で「DX」というキーワードをお客さんに使う事は、実はそんなに多くありません。確かに提案書やプレゼンテーション時、さらには「理想を語る」際(これが一番多いかもしれません)は間違いなく多く使う言葉なのですが、より現場レベルになればなるほど「DX」よりも、まだまだ「デジタル化」「システム化」が主流だと感じます。
そもそも「X」(トランスフォーメーション)に辿り着いた企業がまだまだ少数と思われる中、概念だけが先行している感じがして、お客様の理解と自分の説明は一致しているのか、話しながら違和感を覚える事が意外とあります。
「DX」以外にも、宣伝文句の中に、目新しい言葉、バズワード的なものを安易に使ってしまう我々の業界も、反省すべき点が多々あると考えています(デジタル業界はアルファベットやカタカナ表現が多い業界ですので)。
特に企業のマーケティングやブランディング戦略の中では、そういったキーワードを見せる・発信する事で、リアクションを期待しているケースもあるでしょうから、聞いた側が誤解している、または上手く伝わっていないケースがたくさんありそうです。やはりお客様には「分かり易い」「伝わり易い」言葉で伝えることをしていかなければなりませんね。
弊社も勿論、経産省の「DX認定」を取得し、自社のDX実現へ向けての取組みを進めています。(弊社はデジタル化-デジタライゼーション-の真最中です)
以前より仕事上のいろんなことが効率的になった反面、デジタルが加わると当然アナログも変革を求められますので、手間が増えた部分をさらに改善するなど、全く終わりの見えない取組だと実感しています。DX(=変革)の達成はその時は実感できず、おそらく「気が付いたら変わっていた」と感じるものかもしれませんね。
弊社と同様にDXに取り組まれている皆様も、同じようなお悩み・ご苦労をされていることと思います。この「あきたDX通信」を通じ、「地に足を付けた」「誤解の無い」「分かり易い」DX情報(『芯』のあるDX情報)を継続して発信していくことで、少しでも皆様のお役に立つことを目指してまいります。
<この一年の振り返り ~DXの浸透と実感のギャップ、そして課題(2)~>
話は変わって、DXに関連して最近も少し話題になりましたが、自治体基幹業務システムの標準化について、2025年度末までの移行が遅れる自治体が増える可能性ありとの記事を見かけました。
弊社も自治体のお客様がいらっしゃいますので、決して無関係ではないのですが、なかなか日本全国一斉に標準準拠システムに切替えていくというのは、内容的にも人材リソースなどの面でも難しいものだなと痛感しています。
また、大手民間企業に関するシステム導入に関するトラブルの話題も、皆様いくつか目にされたのではないでしょうか。おそらく発生する被害や金額は弊社の目もくらむような大きなものでしょうし、実際に弊社が担当していることを想像するとゾっとします。
日本全体(世界もですが)のDX推進の動きとして、上述した大掛かりなものも今後益々増えていくと思いますが、弊社も含めた中小企業についても、本格的なDX投資が進んでいくことが、分野・業種問わず各方面で予測されています。
これにともなったデジタル導入に関するトラブルが増えることも想像に難くなく、情報を発信する側、受信する側での相互の誤解や理解不足については(1)で書きましたが、デジタルに関する過度な期待や楽観視など、DX推進やデジタル化でつまずく原因は枚挙にいとまがないでしょう。
「予想と違った」「こんなはずじゃなかった」など、デジタル導入に対する「評価と期待値との乖離」を原因とした苦情をお客様から受ける事は、少なからずあります。
これからが従来と違うのは、DX推進におけるトラブルは、IT業界だけが注意すれば防げるものではなく、お客様と一体となった活動(むしろDXの「X」に関してはお客様主導)で解決を図っていく必要があるという点を強く感じています。
しかしご安心ください。弊社はしっかりとお客様に『伴走』し、共に課題解決をして参ります!
<この一年の振り返り ~番外編~>
身も蓋も無い話になってしまいますが(あくまで個人の感想ですが)、そもそも日本人は、標準化が苦手な人種ではないかと思っています。そもそも「漢字」「ひらがな」「カタカナ」を操り外国人を混乱させ、英語も「カタカナ外来語」にして使いこなしています。
「神道」と「仏教」が見事に共存しているのも不思議です。「和洋折衷」などという言葉も存在し、生活や文化自体が実は複雑で多様性がありますね。
こういった文化や生活にしみこむ背景を理解すれば、画一化したDXを押しつけ型で提案するのではなく、しっかりとお客様と向き合い、弊社やパートナーが持っている知見を活かした提案が良いと考えています。
個人的な話ですが、最近引越しをしました。
不動産関連の手続は勿論、行政、電気、ガス、水道、etc・・・とあらゆる手続きにデジタルが浸透していることを、IT業界に身を置きながら改めて感じました。
非対面で、PCやスマートフォンにポチポチと情報を入力すれば済む世界は大変簡単で便利です。その反面、契約などはやっぱり対面のほうが安心できるなと思ったのも事実で、ケースバイケースで営業での『アナログ感』の演出も大事だな、しっかりやっていこう、と心に決めた9月末でした。
<101回目からの「あきたDX通信」>
さて最後のセクションです。
この「あきたDX通信」では、「DX」にまつわる様々な情報を、分かり易い形でメルマガ会員の皆様に届けるべくやって参りましたが、メルマガの開封率などを見てみると、もっと有用なテーマ・情報をお伝えしなければならないとスタッフ一同実感しています。
皆様にとって、「DX」に対する理解が深まり、「DX」実現へ向けての取組み意欲を高め、もっと「DX」を身近に感じられるコンテンツの充実を図って参ります。これからもご愛読下さいますよう心よりお願い申し上げます。
今後の「あきたDX通信」、スタッフ一同頑張りますので、ご期待ください!
皆様、こんにちは。ADK富士システム 営業の高瀬です。
今回は第101回目、101に因んでDXの入門・始め方について書きたいと思います。
今年7月~9月にかけて、弊社主催でDXワークショップを開催しました。
これは体験型のセミナーで、参加された方には全4回のセミナーと自主課題を通して、社内の問題収集、業務課題の洗い出し、DX・改善対象の選定、DX方針・施策の作成までの一連の流れを体験して頂きました。
また、セミナーの課題とは別にノーコードツール(kintone)の実践講座も実施しました。
こうしたシステム・ITツール導入以前のいわゆる上流工程をテーマとしたセミナーは、弊社主催として初めての試みでした。
開催に当たり不安もありましたが、2社8名の方にご参加頂けました。
どの方もITのエキスパートではなく、普段はそれぞれの担当業務に就いている方でしたが、セミナーの時間以外にも課題に取り組んで頂き、無事DX方針の作成まで終えることが出来ました。
私も一部の講師役とワーク補助のためセミナーに参加しておりました。DXをテーマとしたセミナーでしたが、実は直接ITに関係する話は最終回までほとんどなく、業務プロセスや人に関する事柄についての検討にワークの大半の時間を使っています。
参加された方の目的はもちろん、業務改善やDX人材の育成です。
前回のコラムで引用されていた「第5回秋田県内におけるIT/DXの導入実態に関する調査」からもDX人材・IT人材のニーズが増していることが伺えます。
しかし、DX人材とIT人材の違いって一体何でしょうか?
約1年前の私のコラムでも同じことについて話題にしたのですが、IPA(情報処理推進機構)の「DX白書2021」には、「IT人材」、「現場IT人材」という2つが定義されています。「IT人材」はITエンジニア、「現場IT人材」はユーザ企業でビジネスをデザインする人材です。
今回のセミナーは正に「現場IT人材」となる人に向けたもので、参加された方々は「現場IT人材」としてセミナーを通じて現場DXの糸口をつかんで頂けたのではないかと思います。
本セミナーの次回開催は今のところ未定ですが、
引き続きDX関連セミナーの企画・開催を続ける予定です。
「現場IT人材」を目指される方がいらっしゃいましたら、次の機会に是非ご参加頂ければと思います。
<DXに関するお問合せ先>
エイデイケイ富士システム株式会社
DXセンター DX担当までお申し付けください。
TEL:018-838-1173
Email: dx-lab@adf.co.jp
---------------------------------------------------------------------------------------
あきたDX通信>>>>> 編集長 伊嶋謙二 /// 編集スタッフ 伊藤真弓 澤田亜弓 /// 主幹:五十嵐健 /// エイデイケイ富士システム株式会社
Copyright(C)、エイデイケイ富士システム株式会社、掲載記事の無断転載を禁じます。